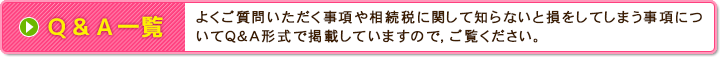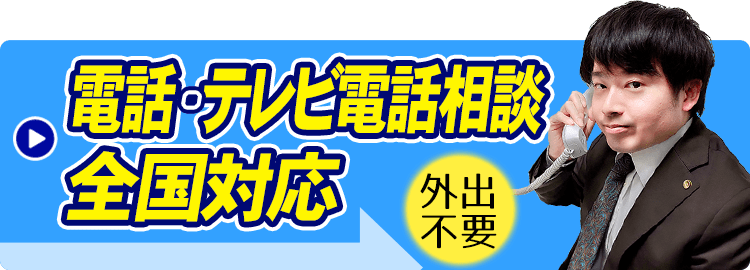お役立ち情報
相続税の申告期限はいつか
1 相続税の申告期限
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。
これは、相続税法第27条第1項に定められています。
条文自体は長いので、このコラムの末尾に示すので参考になさってください。
この条文を大まかに分解すると、以下の通りとなります。
(ア)相続又は遺贈により財産を取得した者は
(イ)相続財産の課税価格が、基礎控除額を超えるとき
(ウ)かつ、当該相続人の事情(配偶者控除、障害者控除等)による計算をした結果、それでも相続税額があるとき
(エ)その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内
(オ)相続税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出する(申告)
2 相続の開始があったことを知った日について
相続は、被相続人が死亡した日から開始します(民法第882条)。
例えば、同居している父親が、闘病の末、自宅で息を引き取った場合、その相続人である長男が同居しているなら、長男にとっての相続の開始(被相続人の死亡)があったことを知った日(起算日)は、まさにその死亡日であると言えます。
また、結婚して家を出たため、父親と同居はしていなかったが、長男からの連絡を受け、父の自宅に飛んできた長女は、長男から連絡を受けて被相続人の死亡を知った日が起算日になります。
それでは、20年前に家を飛び出して、連絡も取らずに長年家を空けている次男の場合はどうでしょうか。
実際に、税務署に対して事情を説明し、父の死を全く知らなかったということが認められれば、実際に知った日から10か月ということになるものと思われます。
しかし、日本における通常の環境下であれば「家族であれば大抵、連絡も取れるでしょう」「家族である父の死という重要な話であれば、なおさら家族も連絡するでしょうし、連絡も受けられるでしょう」と考えられますので、なかなか「全く知らなかった」ということは認められにくいと考えられます。
そこで次男としては、日本における通常の環境下にいなかったなど、本当に音信不通であったこと、そして父の死を知らなかったことを税務署に納得してもらうには、少なくとも、例えば外国への渡航証明、居住証明など相応の証拠が必要になるものと思われます。
このような次男のケース以外でも、「相続の開始を知った日」が被相続人の死亡の日と一致、又は近接しない場合があります。
相続税法基本通達27-4という、政府から出された通達があり、この通達にはいくつかの例外が認められています。
ア 失踪宣告に関する例外(1~3)
イ 認知、嫡出否認、胎児、幼児に関する例外(4~7)
ウ 遺贈、条件付き遺贈に関する例外(8、9)
いずれも、自身がその被相続人の相続人であると知りようがない状況下ではどうしようもありませんので、「事情を知ったことにより、自身が相続人であると知った日」を起算日とすると定めています。
遺贈(8)の例で言うと、自分が遺贈を受けていることを知らなければ、自身が受贈者で相続税申告が必要なことも知る由もありません。
だから、「遺言書等を見るなどして、自身に対する遺贈があったことを知った日」を起算日とするということです。
3 10か月以内の申告をしなくてもよい例外について
原則として、起算日の翌日から10か月以内に相続税申告をしなければなりません。
申告しない場合は、相続税法上の相続税計算の特例適用を受けられない、無申告加算税を課されるなどのペナルティを受けることになります。
ただ、どうしても申告が難しいと明らかに認められる場合には、その理由のやんだ日から二か月以内に限り、当該期限を延長することができます(国税通則法第11条)。
その理由として「災害その他やむを得ない理由」と定めていますが、例えば、2024年の能登半島の大地震などがそれに該当します。
つまり、大きな災害等がない限り、そういった期限延長は認められないともいえるのです。
4 遺産分割協議が整わない場合
たまに聞かれるのは、「遺産分割協議が整わないので、相続分が決まらず、相続税申告ができない。だから遺産分割協議が整うまで申告期限を延長してほしい」という話です。
そのような理由で延長ができれば良いのですが、これまでの話の通り、そういった理由は申告例外に当たらず、起算日のずらしもできません。
そこで事実上、以下のような対応をすることになります。
ア まずは、本来の申告期限までに法定相続分での相続税申告を行います。
イ 同時に「申告期限後3年以内の分割見込書」なる文書を管轄税務署に提出します。
ウ 後日、遺産分割協議が整った場合、その遺産分割協議に基づく、修正申告(税額を実際よりも少なく申告していた場合)または更正請求(税額を実際よりも多く申告していた場合)を行います。
いずれにしても、以上の申告等を怠ってしまうと、相続税計算における税率等軽減、計算の特例の適用を受けられなくなってしまう可能性が高くなりますので、申告を怠らないことが第一です。
5 相続税申告についてはお早めにご相談を
以上から、相続税の申告期限は「その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内」で、その期限は、既述のとおり、よほどのことがない限りずらせません。
早めに、税理士に相談・依頼をするなどして、申告期限を徒過しないようにすることが賢明です。
参考条文 相続税法第27条第1項
「相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した者及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は(ア)、
当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において(イ)、
その者に係る相続税の課税価格(第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)に係る第十五条から第十九条まで、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定による相続税額があるときは(ウ)、
その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(その者が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に(エ)
課税価格、相続税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(オ)。」